2011.11.04 Friday
それから丁度一年が経ち、僕達は二回生へ進級し、
それに伴い二十歳になった。
特に何か変化があったわけでない。
文ちゃんは相変わらずピンと伸ばした背筋と涼しげな顔で歩き、
大学のキャンパスに華を彩どおっていたし、
芳樹君は大勢の友人に囲まれつつも、
奇特なことに僕のような地味な人間とも変わらず仲良くしてくれていた。
そんな二十歳の、すっかり秋めいたとある日の夜。
「あ……」
思わず声が漏れる。
視線を下げると、優しく微笑みを浮かべる文ちゃん。
僕はどことなくいたたまれない気持ちのまま、
すでに柔らかくなりはじめた陰茎を彼女の中からゆっくりと引き抜く。
あれから一年ほど経つのに、未だに彼女の膣の刺激は、
僕をまさに三擦り半で射精に誘う。
果たしてこんなのがセックスと言えるのだろうか。
この事に関して、何も責められないというのが逆に肩身が狭い。
以前に一度、あまりにも早く射精してしまうことに関して、
意を決して文ちゃんに謝罪交じりの相談をしたが、
彼女は「何が問題なんだ?」ときょとんとした表情で首を傾げていた。
彼女の性行為に関する見解は、初体験のころから変わっていない。
あくまで愛情を確かめ合う行為と、子作りの為のもの、と一環している。
ただ男の性欲やそれに対するプライドも、理解はしようと努力はしているようで、
あまりその事については口に出さないようになっていた。
彼女にとっての『本番』とは、僕が射精した後、
淡い空気の中、ベッドの上で互いの暖かさを感じ合ったり、
愛を伝えあったりすることだと思っている節がある。
それはそれで彼女の愛情を窺い知れることができて、
僕としては不満があるはずもないのだが、
やはり男として、恋人を性的快感で絶頂させたい、という野望は捨てきれない。
「バイブとか使ってみたら?」
ついついこんな下世話な相談を芳樹君にしてしまった結果がこれだ。
「ははは……」僕は苦笑いで答える。
「まぁ、別にそこまで気にする必要ないんじゃねえの?
お前らほどラブラブなカップル見たことねえぞ?」
「そうかな」
「そうさ」
軽口を織り交ぜながらも、きちんと相談に乗ってくれる芳樹君に、
僕はとても感謝をしていたし、そして信頼もしていた。
その一方で、文ちゃんはやはりどこか芳樹君に対して壁があった。
もう彼との付き合いも一年以上になるのに、
彼に対して露骨な警戒心を露にする場面も何度か見かけた。
僕はそれがイマイチ理解が出来なかったが、
彼女は彼女で僕の友人関係に口を出さないのだから、
僕にもとやかくいう権利はないと黙っていた。
そんなある日。
芳樹君が主催した飲み会がとある大手居酒屋チェーン店で開かれていた。
その晩集まった何十人といる飲み会メンバーの中で、
何故この飲み会が開かれたかに興味がある人間は居ない。
いつも通りの集まり、といった認識が殆どだろう。
ただしあくまで芳樹君の思惑としては、
明日イギリスへと短期留学する僕への送別会のつもりだったのだ。
勿論僕の大学内でのヒエラルキーは相変わらず、
『あの』桐島文の彼氏、という称号さえなければ空気のようなもので、
実際この飲み会で僕に話しかけてくるのは精々数人といった程度だ。
とはいえそれくらいが丁度居心地が良いと、
僕は慣れないお酒をちびちびと口に運んでいた。
「もう準備は済んだのか?」
アルコールの所為か、いつも以上に艶かしく見える文ちゃんがそう尋ねてくる。
「うん。もうばっちり」
自信満々にそう答える僕とは対照的に、
「そうか」と寂しそうに微笑む彼女。
「留学って言っても数ヶ月だけだからね。
荷物なんてたかがしれてるよ」
僕の返事に一呼吸置いて、
「うん」と彼女は小さく首を縦に振ると、
「短期でも、見聞を広める良い機会だ。楽しんでくるといいさ」
そう言うと、文ちゃんは手元にあった梅酒をぐいっと喉に放り込む。
文ちゃんもあまりお酒は好きなほうではない。
というか僕よりも弱いはずだ。
なのに今日はやけにペースが早い。
僕の留学に関して、なにかしら思うところがあるのだろうか。
「お、良い飲みっぷりだね」
不意に背後から掛かる声。
振り返るまでもなく芳樹君だった。
「あ、芳樹君。ありがとね。こんな飲み会開いてくれて」
「良いってことよ。どうせ飲みの口実だけが欲しい奴が殆どだしな」
そう言いながら腰を下ろす芳樹君に、
「そういう言い方は無いんじゃないか安藤君?」
と文ちゃんが少し嗜めるように言った。
「主賓をないがしろにするような言い方は失礼だと思うぞ」
続けてそう口にする。
酔いが回っている所為もあってか、その口調には棘があった。
今日の文ちゃんは少し苛立たしげだ。
僕と芳樹君は困ったように視線をやり取りする。
「ま、まぁまぁ。折角厚意で開いてくれたんだから」
「いや、まぁ俺も言い方悪かったよ。ごめんな」
芳樹君がそう謝ると、文ちゃんもバツが悪そうに、
「い、いや、私の方こそ、つい……すまない」
と素直に謝罪した。
芳樹君は重苦しい空気を阻止するようにぱっと笑顔を浮かべると、
「いいってことよ。あれだろ?桐島さんも寂しいんだよな?」
とからかうように言った。
文ちゃんはただでさえアルコールで染まった頬を赤くして、
「なっ!?」と目を見開いた。
「ああそうなんだ?」と僕もそれに便乗して、文ちゃんをからかう。
「ば、馬鹿」
と苦々しい表情でそっぽを向く文ちゃんは、珍しくどこか幼い雰囲気を醸し出していた。
人気者の芳樹君が他のグループに連れられていって、また僕と文ちゃんだけの空間になる。
彼女は先ほどのやり取りを拗ねているのか、
どことなく口を開きたくなさそうな空気を感じる。
溜息も多い。
僕は机の下でそっと彼女の手を握る。
「寂しい?」
彼女は下唇をぎゅっと噛み、
「……寂しくない」と口にすると、
一呼吸置いて「…………わけがないだろう」と呟いた。
「僕も寂しいよ」
何故だか笑みが浮かんでくる。当然僕だって寂しい。
でも不安はない。
文ちゃんもそんな僕につられて呆れたように微笑む。
「気をつけて、無事に帰ってきてくれ」
「戦場に行くんじゃないんだから」と僕は笑った。
実際のところ、僕が海外留学を決めた理由に特別なものなどない。
普遍的な若者にありがちな、好奇心と向上心を満たすためのものだ。
僕は以前ほど、自分を卑下するような人間ではなくなった。
何かとつけ、文ちゃんや芳樹君に対して劣等感を抱いていた自分はもう居ない。
それはきっと、文ちゃんと密接に心も身体も重ねあった時間が、
僕を変えてくれたんだと思う。
ただ、真っ直ぐに世間を見ることが出来れば出来るほど、
やはり文ちゃんや芳樹君が、如何に優れた人間であるかがわかるようになった。
それに対し、卑屈にならず、きちんと自分と向き合うようになれたのは、
胸を張って成長を自己評価したい。
「それにしても、桐島さんは反対しなかったの?」
お開きになった飲み会の後、芳樹君は僕達を一人暮らししている部屋へと誘ってくれた。
そこで3人で飲み直しというわけだ。
「何を反対することがある?」
その声に、相変わらず棘が生えているのは、
いつも以上に酔いが回って本心が見え隠れしている、
というだけではない。
本来ならば、今頃僕と文ちゃんは、二人で僕の部屋にいるはずだった。
それを芳樹君に、強引に誘われた、と彼女は思っているのだろう。
『最後の夜くらい、二人でゆっくりしたかった』
と先ほど、隣に座っている文ちゃんからメールが送られてきた。
最後とはいえば最後だけど、少し大袈裟だ。
たかが数ヶ月なんだから、と嗜めて説得するようなメールを、
隣に居る文ちゃんに向かって返信する。
彼女はそれを確認すると、溜息をついて、
また手元のお酒をぐい、っと飲み干した。
今日は本当にピッチがすごい。
「でもやっぱり寂しいんじゃない?」
と芳樹君が質問を続ける。
「良作が決めた事だ。私は応援するだけさ」
とどこか諦観めいた表情でそう答える。
実際彼女は反対はしなかった。
でもその意志を伝えた時に浮かんだ寂しそうな表情は、ちくりと僕の胸を刺したんだ。
僕の携帯が震え、着信を伝える。
また文ちゃんからのメールかと思えば、見知らぬ番号からの着信だった。
電話を取ると、それは先ほどまで居た居酒屋の店員さんで、
どうも僕の身分証明書などが店内に落ちていたとのこと。
僕はお礼を言って電話を切ると、
その旨を文ちゃんと芳樹君に伝え、そして部屋を出て店に向かった。
文ちゃんは一緒に来ると言っていたが、そんな遠いわけでもないので、断った。
(まさか、この男と二人きりになるとはな…)
飲み会の後は、良作の部屋へしけこむことになっていた為、
油断して飲みすぎていた自分自身を、桐島文は不覚と責めた。
慣れない酒が進んだのはそれだけの所為ではない。
そう。
安藤芳樹が言うように、彼女は寂しかったのだ。
照れ隠しのため、冗談めいて口にしたが、寂しくないはずがない。
付き合うきっかけさえ薄い理由だったものの、
いざ恋人になり過ごした二年という時間は彼女に、
充分すぎるほどに、良作に対し、恋心を抱かせていた。
ここ最近。彼女はふと一人で笑ってしまいそうになることがある。
あれだけ、興味が無かった恋愛沙汰に、すっかりと嵌ってしまっている。
良作が他の女友達と話しているのを苦々しく思ってしまったり、
(勿論そんなこと、口に出したことはないだ)
友人に、彼氏に対する女性としての振る舞いを相談したり、
夜中、彼のことを想い、なかなか寝付けなかったり。
今までの自分なら、想像も出来ない、と彼女は自嘲気味に笑う。
いつだって一緒に居たい。
いつだって、良作のことを第一に考えている。
そんな彼が、数ヶ月の事とはいえ、
完全に自分の前から消えてしまうのは、
幼馴染の彼女にとっては初めての経験だった。
最近では、良作の部屋に泊まった時は、
彼の寝顔を眺めながら溜息をよくつく。
溜息で済むならまだ僥倖といえよう。
彼女達はまだ学生の身。
毎晩のように床を共にするなど不可能に近い。
実家のベッドで、一人布団にくるまり、
良作が居ない数ヶ月の生活を想像すると、
ついつい目頭に何かが溜まりこんできてしまう。
(馬鹿馬鹿しい……)
そう嘯きながらも、自分がただの弱い女であることを自覚する。
最大の安心は、愛する男性の腕の中で得られることを知ってしまった。
しかしだからこそ、良作の足を引っ張ることだけは許されなかった。
高校を卒業した辺りから、彼が向上心に目覚めたことは彼女も気付いていた。
それは彼女にとっても良い刺激になり、
お互い認め合い、そして成長しあう理想の関係だと彼女は考えていた。
以前はどこか感じた良作の頼りなさはみるみると消えていき、
それと反比例して、いつの間にか、彼女は自分の弱さを気付くようになっていった。
その契機は、やはりセックスだったのかもしれない。
自分が女であると、気付かされた人生で数少ない経験。
巷に聞く性的快感というものこそ感じたことはないが、
愛する男性の腕の中で組み敷かれる恍惚は、
彼女が実生活や剣道で育んできた価値観を一片させた。
強くあらねばならない。
元々彼女が求めた強さとは、相手を屈服させるための道具ではない。
誠実に、そして優しく生きる為の手段だ。
その考えは今でも変わっていない。
しかし、何だろう。
良作に抱かれている間(といっても三擦り半の間だけだが)
下半身から頭に穿たれる甘い電流は、
彼女のこれまでの人生を否定とまでは言わないが、
どこか嘲笑われてるかのような気さえした。
良作が果てた後もなお続く下半身の疼きは、
彼女自身も気付くことなく蓄積されていた。
「桐島さんってさ」
良作が出て行った後、彼女は一切酒には手をつけなかった。
「ん?」
それでも酔いは、彼女の真っ白な頬を紅潮させる程度には残っていた。
「良作のどこが好きになったの?」
これだ。
この眼が気に入らない。
良作をどこか見下す眼を、彼女は嫌悪した。
「全部だ」
酔いで火照る頭でも、明瞭かつ迅速にそう返事をした。
「ふーん。勿体ないと思うんだけどな」
その言葉にカチンと来る。
手元に竹刀があれば、間違いなく抜いていただろう。
「どういう意味だ?」
睨みつけるようにそう問い詰める。
「いやそのまんまの意味だけど」
ついに本性を現したかと、鼻息が荒くなる。
「良作は私にとって唯一無二の恋人だ。誠実で、実直で、努力家で。
どれだけ端正な容姿をしてようとも、どれだけ多くの友人に囲まれようとも
あの人以上の男性など私には存在しない」
たとえ酔いが回っていようとも、
良作を愚弄されたとあっては、
彼女の口は実に滑らかに啖呵を切った。
普段から、心の奥底で思っていることだからこそ出来る芸当だろう。
しかしその彼女の真摯な言葉を、
「超早漏でも?」と安藤芳樹は嘲笑う。
「ッ!貴様っ!」
肩膝を立て、握りこぶしを作る。
安藤は、落ち着いた表情で、両手の平を前に突き出す。
「まぁまぁ落ち着いて」
その言葉など意に介さぬように、彼女の顔は既に怒りで真っ赤だ。
それは酔いの所為ではない。
「ごめんごめん。俺も酔っちゃっててさ。ついね」
彼女は一度だけなら、と溜飲を飲む。
姿勢を戻しながら、しかし彼を睨みつける。
「普段から、そうやって良作を見下しているのか?」
「そんなわきゃないじゃん。良作も大事な友人の一人さ。
でも正直、文ちゃんは勿体なくない?あんな空気みたいな奴」
「……っ!」自制のため、彼女は自身の太股を強く握る。
良作の友人でなければ、その選択肢は無かっただろう。
「……良作が帰ってきた後、彼に対して謝罪しろ」
「なんて?」
「さっきの言葉に対してだ」
「なんでわざわざ」と笑った。
「じゃあせめて代理として、私に謝罪をしろ」
「でも事実なんでしょ?」
彼女の腸はすでに煮えくり返っていた。
酔いさえなければ、数発引っ張たいて、良作を連れて帰っていただろう。
いやむしろ逆に、酔っているからこそ、感情をコントロール出来ないのか。
どちらにせよ、彼女の怒りは収まらない。
「他人を貶すのは、自分に自信がな無いからか?」
売り言葉に買い言葉。
彼女はらしくない対応を見せる。
自身の精神の未熟さを恥じながらも、
どうしても目の前の男を許せなかった。
「どういう意味?」
「矮小な心の持ち主には、それに見合った男性としての器が備わっているのだろう?」
挑発するように、見下しながらそう言った。
安藤は鼻で笑い、
「試してみる?」と余裕ありげに言った。
「結構だ。間に合っている。そうでなくとも、粗末なものに興味もない」
嫌悪感を隠そうともしない文とは対照的に、安藤は涼しげな顔のまま、
「じゃあこうしよう。もし俺が桐島さんをイカせれたら、俺の勝ち」
「馬鹿馬鹿しい」一笑に付す。
まさに幼稚の極みと内心馬鹿にする。
「俺が負けたら、良作に謝るよ」
「……すぐに帰ってくるだろう」
「だからそれまでの時間で良いよ?
勿論挿入も無しで良い。
どうせ入れちゃったらアヒアヒ喘ぐんだろ?
だからあくまで前戯だけ。
どう?これだけハンデあってもビビってる?
あんなセックスしょぼそうな男で満足してるくらいだから、
すぐに自分から腰振っちゃうとか?」
やらしげな笑顔を浮かべてそう言った。
人を小ばかにした、嫌な笑顔だ。
彼女の頭の中で、何かが切れる音がした。
「…一つ条件をつけろ」
「何?」
「私が勝ったら、二度と良作には近づくな」
その平坦な口調には、抑えきれない怒気を孕んでいた。
安藤は鼻で笑い、「OK」と愉快そうに口にする。
膝歩きで近づいてくる安藤に、鳥肌がたつほどの嫌悪感を抱きながら、
愚かな挑発に乗ってしまったと後悔する。
しかし、それ以上に、この男が許せなかった。
へらへらと友達面で恋人に近づき、
その実内心では愚弄し続けていたであろうこの男を、
彼女は殺意に近いほどの憤怒を覚えていたのだ。
もう良作には近づかせない。
こんな男の愛撫で感じるわけがない。
嫌いな人間に触られて、性的快感など感じるはずもない。
嫌悪感をかき消すように、自身の勝利を確信して心中でほくそ笑みながら、
文は安藤芳樹を睨みつける。
-------------------------------
居酒屋で手渡された免許証などをポケットに仕舞いこむと、
僕は芳樹君の部屋に戻るため足を前に運んだ。
電灯に照らされた夜道をセンチメンタルな気分で歩く。
(電柱だらけのこの光景も、明日でしばらくお預けか)
それにしても、と思いなおす。
芳樹君はなんて友達思いなんだろうと。
僕のような友人のためにあんな飲み会を開いてくれて、
更にはその後自分の部屋に招待してまで二次会をしてくれるなんて。
僕は最高の恋人と、友人を持てて幸せだ。
幸運すぎて怖いくらいだ。
その感情は、明日からの海外留学に、益々熱をともす。
彼らの友人として、恋人として、より一層自分を磨きたくて仕方がない。
そんな事を考えながら、アパートの階段を昇る。
芳樹君の部屋を確認して、ドアノブに手をかけると、何故か鍵がかかっていた。
僕はもう一度表札を確認する。
間違い無い。
仕方なくインターホンを鳴らした。
待つ。
反応はない。
僕は首を傾げて思案する。
(二人でコンビニでも行ったのかな?)
しかし中からガタガタと物音がした気もする。
とにかく僕は携帯を手に取ると、それと同時にドアが開いた。
「あ、悪い悪い。ここの鍵ぼろいからたまに勝手に掛かっちゃうんだよな」
と、苦笑いを浮かべながら芳樹君が出迎えてくれた。
「確かにここ結構古いもんね。引越ししたら」
そう言いながら靴を脱ぐ。
「ま、住めば都ってなもんさ」
そんな会話をしながら居間に上がると、
少し様子のおかしい文ちゃんの姿があった。
たとえ酔おうが、常に変わらない背筋の綺麗な文ちゃんが、
少しうなだれるように座っている。
「ああそういえば桐島さん、ちょっと体調悪いらしいぞ。な?」
と芳樹君が文ちゃんに確認を取るようにそう言った。
文ちゃんは返事をしない。
芳樹君を見ようともしない。
顔が赤く、どこか息苦しそうでもあった。
それは酔いというよりは風邪の症状に見えた。
「大丈夫?」
文ちゃんは崩れた座り方をしたまま僕を見上げた。
その瞳は、これまで見たことがないほどに弱弱しい。
うっすらと涙すら浮かんでいる気がする。
何かを訴えたいかのような、悲しそうな表情。
「帰ろっか」
僕が心配そうに手を伸ばすと、
彼女は無言で俯いて、そして僕の手を取った。
「気をつけて帰れよ」
「うん。今日はありがとね」
「いいってことよ。明日見送りに行くかな」
芳樹君がそう言った後、気のせいか、
僕の手を握る彼女の手が震えた気がする。
「本当?ありがとう」
「ああ。じゃな」
僕達は芳樹君のアパートを出ると、
「大丈夫?歩ける?」と彼女に尋ねた。
文ちゃんは力なく頷くだけだ。
こんな彼女は見たことがない。
僕は心配になって、「病院行こうか」と提案した。
すると彼女は、俯いたままふるふると首を横に振り、
「少し……飲みすぎただけだから。
そう……お酒の、所為、だから」と呟いた。
その後、予定通り彼女は僕の部屋に泊まった。
僕は彼女の体調を慮って、家に帰るよう言ったのだけれど、
「……どうしても一緒に居たいんだ」と彼女は聞かなかった。
しばらくは離れるのだから、一緒に居たいのは僕も同じだった。
ベッドの中で、彼女は僕の手をずっと握っていた。
暖かかった。
すべすべで、柔らかい手。
剣道有段者とは思えない。
彼女と付き合うようになって、僕は文ちゃんがただの女の子だということを知った。
超人なんかではない。
か細く、柔らかい、どこにでもいる普通の女の子なんだ。
正直僕はセックスをしたかったけれど、体調不良なら仕方ないと、
せめてこの手の平の感触を楽しんだ。
そんな折、芳樹君の部屋を出てから殆ど喋らなかった文ちゃんが、
「……好きだ……愛してる」と呟いた。
「僕もだよ」と頭を撫でながらそう返す。
彼女はまた瞳に涙を浮かべて、でも僕の眼をじっと覗き込み、
「良作が……好きなんだ」と囁いた。
きっと、彼女も寂しいんだろう。
距離が離れることに不安があるのは僕も一緒だった。
だから気持ちを確認しあいたくて、
僕達は一晩中愛を囁きあった。
-------------------------------
「それじゃ」
トランクを片手に、彼は二人を振り返ると、そのまま空港奥へと消えていった。
桐島文はその背中を名残惜しそうに見つめ続けた。
その視線に気付いたのか、それとも彼も同じような気持ちなのか、
もう一度振り返り、そして彼らは小さく手を振り合った。
今度こそ、良作の姿が消えていく。
粒のように小さくなっていく恋人の背中を見つめながら、
文は一つのジレンマに捉われる。
このまま彼の背中を視線で追い続けたい、という気持ちと、
今すぐこの場を離れたい、という気持ち。
前者は説明の必要が無いだろう。
後者は彼女の横で、へらへらと彼女の横顔に視線を向け続ける男のせいだ。
完全に良作の姿が消える。
彼女は小さく溜息をつくと、もう何の用もないと、
迅速に踵を返してその場を去ろうとする。
出来る限り早足で、カツカツと靴音を鳴らしていく彼女の背中に、
無言でついていく安藤芳樹。
「お茶でもしてかない?」
「断る」
声が掛かった背後に一瞥もせず、
彼女は前だけを見据え、はっきりと拒絶した。
「つれないなぁ」
そんな声など意にも介さず、彼女は意地でも振り向かない。
口をへの字に結び、ただひたすらと帰路に急ぐ。
「そういや昨晩の勝負って途中だよね」
その言葉に、鼓動が跳ね上がる。
一瞬足を止めてしまいそうになるが、
ますます険しい表情を浮かべ、
彼女は握りこぶしを作り、歩幅を大きくした。
思い出したくもない昨夜の回想が頭をよぎる。
『そんじゃ早速……』
念のためにとドアに鍵をかけた安藤は、
憮然とした表情の文の傍に座り直し
そう言いながら彼女の太ももを撫でた。
彼女はその感触に、全身が総毛立つ。
気色悪い。
想ってもいない、むしろ嫌悪さえしている異性に触れられるのが、
こうも気分の悪いことだと思ってもいなかった。
もう彼女の頭には、勝負のことなど頭にはなかった。
感じる感じない以前の問題だ。
早く終わって欲しい。
全身に鳥肌を立たせながら、負けなど有り得ない、
と確信しながらも、ただ良作に対する罪悪感だけが胸をちくりと刺す。
しかしだからこそ、それほどまでに良作を想うからこそ、
この男に一泡ふかせてやりたかった。
男性として、未熟だと罵ってやりたかった。
そして一番の理由は、もう良作に近づかせたくなかったのだ。
彼女はそれだけを矜持に、蛇のように身体を這いよる安藤の手の感触に耐えた。
『くそっ……』
思わずそう悪態をついて身を捩ったのは、
彼が執拗に性器や乳首など、いわゆる性的な箇所を避け、
太股や腰、背中や脇腹などだけを、
まるでマッサージのように愛撫し続けた結果、
自身の身体が少しづつ火照っているのを感知してしまったから。
『んっ……』
安藤の手は、強すぎず弱すぎず、絶妙の力加減で彼女の身体を按摩した。
時に指だけで軽く引っ掻くように脇腹を刺激したり、
介護するかのように背中を撫でたりもした。
その所為か、ぞわぞわとした感触が全身に広がる。
しかし彼女はそれを嫌悪感によるものだと思い込んだ。
勿論それもあるだろう。
しかし身体の奥底からふつふつと熱を帯びてくる感覚は、
それだけでは到底説明が付かないものだとは、
薄々彼女も感じ始めていた。
(触るなら……早く触れ……!)
まるで身体をほぐす事だけを目的としたような安藤のその手つきに、
文は苛つきすら覚える。
10分?
20分?
性的な部分を避けた愛撫は執拗に続いた。
歯噛みをして声は我慢しているものの、
時折鼻からは荒い息遣いが漏れ、
そして安藤の手や指に誘導されるように、
彼女は踊るようにそのしなやかな身体を捩じらせていた。
屈辱だった。感じている、とは認めたくはない。
(そうか……お酒の所為か……)
彼女は言い訳を探した。
とはいえあながちそれも間違いではない。
実際、多量のアルコール摂取も大きな要因の一つだったろう。
しかしそんな事は今は関係ない。
ただ彼女が、良作に対する罪悪感への免罪符を必要としただけのこと。
彼との勝負とは何も関係が無い。
酒の所為にしようが、どうだろうが、
彼女の乳首は痛いほどに勃起していた。
小さな乳輪に乗った、薄桃色のやはり小さな乳頭は、
男性に触れられるのを求めるかのように、突起していた。
彼女は自身の呼吸を諫めようと意識するばかりで、
そんな身体の変化に気付かない。
そこへ、ようやく、安藤の指が胸元へ伸びる。
数度、その手の平が、服越しとはいえ容易にわかる、
美しく、適度に豊かな彼女の乳房を楽しむと、
人差し指と親指が、まるで透けて見えていたかのように、
服の上から、勃起しきった乳首を強く摘みあげた。
『んっ……あっ!!』
その刹那、彼女は自らの身に何が起こったのか理解出来なかった。
彼から逃げるように、やや丸まっていた背筋は弓のように仰け反り、
そして口からは甲高い声が漏れた。
(……な、なんだ?)
感電した。彼女は本気で、そう思った。
そこで初めて、彼女は自分の乳首がいやらしく勃起していた事に気付く。
再び彼の指に力が入る。
『やっ……ま、待てっ!』
そう言いながら、彼女は慌てて彼の手に両手を重ねる。
今までは、屈強な精神力で為すがままで耐えてきたが、
先ほど流された電流は、彼女に未知の恐怖感を与えた。
(な、なんだ……?なんださっきのは?)
切羽詰った彼女とは対照的に、
へらへらとリラックスした口調で、
『抵抗したら俺の勝ちね』と安藤は言い放つ。
『なっ!?なにを勝手なことを!?』
『そりゃそうでしょ。抵抗するって事はやばいって事でしょ?』
『……ば、馬鹿な!貴様なんかに……くっ……あるわけない!』
『別に感じても良いよ?イったら負けってだけだし』
安藤は楽しそうに、そう言いながら、
彼女の乳首を摘み続ける。
『んっ……くっ……んあ…………くぅっ」
彼女は歯軋りをしながら声を我慢し、再度背中を丸めながら、
その感覚に耐える。
快感、とも認識が出来ない。
それは彼女にとって初めての感覚。
ひたすら電流を流され続ける、一種の責め苦。
しかしその電流が、次第に甘く感じる。
(……何だこれ……腰が浮く……)
もう彼女は、歯を食いしばるので精一杯。
少しでも気を緩めば、口から何か出てしまいそう。
甘く、蕩けきった、今だかつて、
良作はおろか、自分すら聞いたことがない、
甘く蕩けきった何かが出てしまいそうで怖かった。
それは恋人に対する裏切りだと強く感じた。
良作以外には誰にも聞かせてはいけない。
そんな声が、喉元まで来ている恐怖に彼女は耐えた。
彼女のそんな意識を隙をついたのかは定かではないが、
安藤の指が、さりげなく彼女の服の下に滑り込み、
そしてそれは、直接彼女の乳首を強く摘み上げた。
『いっ……んっ……』
彼女は声にならない声を上げる。
歯を喰いしばったままでいられたのは、
彼女の意思というよりも、
硬直した身体のおかげと言うべきかもしれない。
とにかく、喰いしばった彼女の口からは、
『あっ……いっ……』と囁くような声が漏れ続ける。
それと同時に、ぴくぴくと、小さく、しかし長く痙攣する身体。
『あれ?乳首だけでイっちゃったの?感度良すぎ』
と愉快そう笑う安藤の声は、彼女の耳には届いていない。
それが性的絶頂なのかどうかは、彼女にもわからない。
経験したことがないからだ。
ただぐわんぐわんと視界が揺れる。
何も考えられない。
そんな中、彼女の思考は、
(嘘だ……嘘だ……)と、
ただひたすらに繰り返すだけ。
何とか両手を支えに姿勢を維持するが、
なかなか整わない呼吸と鼓動。
纏まらない思考。
その時、ドアノブがガチャガチャと回る音。
その直後に聞こえる安藤の舌打ち。
彼女は安堵の感覚に捉われるも、
徐々に鮮明になる思考回路は、
度し難い罪悪感と敗北感に覆われた。
その後、良作の部屋に泊まり、彼の隣で一晩過ごした彼女は、
ほとんど一睡の眠りにつくことは出来なかった。
良作の部屋に入ってすぐにトイレを借りた彼女を驚愕させたのは、
脱いだショーツと自身の秘部の間にべっとりと糸を引いた粘液。
彼女はそれを見た瞬間、両手で顔を覆い膝から崩れた。
(馬鹿な……)
自分が女であることを恥じた。
生理反応とはいえ、良作以外の男を受け入れる準備をした、
自分の身体を呪った。
その後、良作の寝顔を眺めながら、彼女は悶々とした気分に襲われた。
しかしセックスを誘うことは躊躇われた。
誤解とはいえ、彼が、自分が体調不良だと心配してくれていたから。
彼女は、生まれて初めて、自慰をした。
その行為の存在は勿論知っていたが、
作法などは誰に教えてもらったものでもない。
勝手に、彼女の指が、身体の要求に応えるように動いた。
自然と彼女の手はパジャマの上からクリトリスを刺激し、
声を押し殺したまま、静かに性欲を処理した。
微かな甘い吐息と共に、その余韻に浸りながらも、
彼女は惨めな気持ちで一杯になった。
火照った身体は、男を欲した。
無理矢理犯されたい、とすら思った。
でもそれは適わぬ願い。
聞こえてくるのは、留学を明日に控える、
恋人の安らかな寝息。
彼女は、それを眺めながら、何度も何度も、自分で火照る身体を慰めた。
数度目には、初めての自慰による罪悪感からか、
良作に背中を向けて、うっすらと涙を流しながらも自身を慰めた。
時は現在に戻る。
「ねぇねぇ。勝負って俺の勝ちでしょー?」
とうの昔に空港から離れ、電車に乗り、街を歩いても安藤はついてきた。
彼女はひたすら無視をし続けたが、あまりのしつこさに、
いい加減にしろと怒鳴りたい衝動に駆られる。
地元のアーケード商店街のど真ん中。
人通りは閑散としている。
彼女はぴたりと突然足を止めた。
それに伴い彼の足も止まる。
ふぅ、と一つ息を吐いて、彼女は振り向いた。
「私の勝ちだ。イってなどいない。この下手糞」
出来る限り冷めた表情で、かつ見下した視線で振り返る。
安藤は口を尖らせ、「嘘ばっか」と笑う。
「嘘ではない。 学年一の色男とやらもタカが知れてる。
稚拙の一言だな」
彼女は鼻で笑う。精一杯の逆襲。
流石にむっときたのか、安藤は片眉を吊り上げて、
「じゃあもっかいちゃんと勝負しようよ」と苛立たしげに口にした。
「その必要は無い。私は何も気持ち良くなかった。以上だ」
そう言うと、彼女は前を振り向きなおし、そしてその場を離脱しようとする。
その背中に、ぬるりとした、狡猾な声。
「良作に言っちゃおうかな」
文の足は、自動的に止まる。
眉間に皺を寄せて、憤怒の形相で安藤を振り返った。
「貴様……」
「じゃあもっかい勝負してよ。桐島さんが勝ったら、
もう俺二人には関わらないからさ。
でも勝ったら、そのままヤラせてよ?」
「……屑だな」
彼女はぼそりと呟く。
挑発の為でもなく、心の奥底からそう思った。
「わかった。良いだろう。その言葉、忘れるなよ?」
「OK。じゃ、こっち来てよ。ラブホあるから」
そう言い彼女を誘導する安藤の背中を睨みつけながら、
(あの時は、お酒が回っていただけだ。
普段なら、こんな男に感じさせられるわけがない)
そう確信しながら、握り拳を固める。
(もう二度と、こいつとは関わりたくはないし、
良作と関わらせたくもない。
完膚なきまで叩き潰して、吠え面をかかせてやる)
親の仇のように、安藤の背中を睨みつけながら、
黙って後ろを歩く。

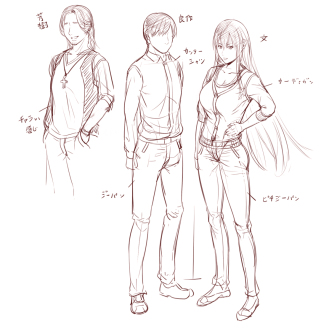



Comments